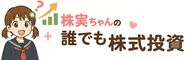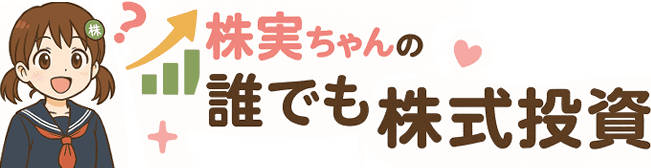こんにちは〜、あたし好奇心まんまんな株実ちゃんです!
そもそもなんで株って名前になったの?って疑問を、あたしが天然ボケ炸裂で聞いちゃうよ〜♪

えーっとね、木の株(切り株)
そうだね、株実ちゃん。今日は語源から、どうして今の「株」になったのかをゆっくり話すよ。
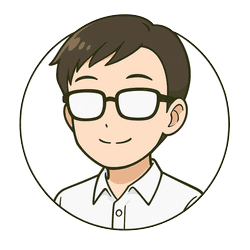
1. まずは漢字の「株」って元々何?
昔の漢字で「株」は本来、木の根元や切り株を意味してたんだ。木の「根っこ」が残るところ、つまり何かの元になる場所ってイメージ。
この「元になる場所」というイメージが、少しずつ「一部分」とか「まとまり」を表す意味に広がっていったんだよ。

へー、木の切り株がルーツなんだ!じゃああたしの心も切り株…って、ちょっとロマンチック?えへへ(お兄ちゃんドキッ)
株実ちゃん、説明と関係ない妄想はほどほどにね。でも語源の雰囲気はそんな感じだよ。
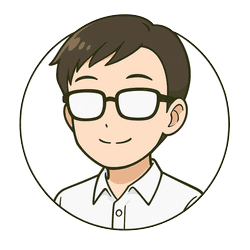
2. 江戸時代の「株」とは?
江戸時代には「株仲間」という言葉があったよ。これは特定の商売や仕事を独占する組織のこと。ここでの「株」は「役目」や「権利」のまとまりを指していたんだ。
つまり「株」は単に木の切り株じゃなくて、『ある人が持つ分け前や権利の単位』という意味になっていったんだね。

へえ〜、独占とか権利ってカッコイイ!でもあたし、独占ってなんかズルい感じ…お兄ちゃん、独占はダメなの?
独占にはいい面と悪い面があるんだ。江戸の株仲間は秩序を守る役割もあったけど、競争を制限してしまう面もあった。そこから徐々に「株=権利」という意味が定着していったんだよ。
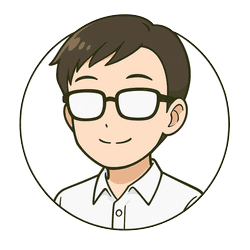
3. 明治以降:西洋の「share」をどう訳したか
明治時代に西洋の会社制度が入ってきた時、英語の「share(シェア)」や「stock」を日本語にする必要があったんだ。
そこで使われたのが「株式」。英語の「share」の意味合いを、すでにあった「株(=一口の権利)」という言葉で表したんだよ。だから今の「会社の一部分を持つ」という意味の「株」が生まれたってわけ。

なるほど〜!英語を日本語にするときに、ぴったりの古い言葉を使ったんだね。お兄ちゃん、ってことは株って会社の根っこをちょこっと持つ感じ
いい表現だね、株実ちゃん。会社の一部、つまり根っこの一片を持つイメージで覚えるとわかりやすいよ。
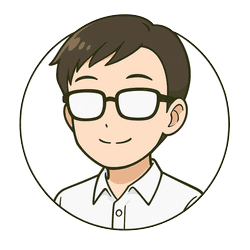
4. 「株」の使われ方:株式・株券・配当って?
現代でよく使う言葉を簡単に整理してみよう。
- 株式:会社の持ち分(所有の単位)。
- 株券:かつてあった、株式を示す紙の証明書。今は電子化が進んでるよ。
- 配当:会社が利益を出したときに、株主に分けるお金。
どれも「株」という言葉が「持ち分」や「権利」を表している点でつながっているんだ。
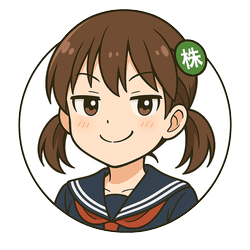
ふむふむ!あたし、配当でお菓子買いたい!お兄ちゃん、配当でデート代ください!えへへ〜(照れ)
株実ちゃん、まずは基礎を覚えようね。配当は会社次第だから確実とは限らないけど、分かると面白いよ。
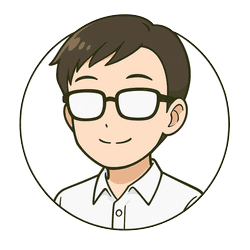
5. まとめ:名前の由来を一言で言うと?
長くなったけど、要するに「株」という名前はこういう流れで今の意味になったよ:
- 元は「木の切り株」などの「根っこ」を意味してた。
- そこから「一部」「まとまり」「権利」を表す言葉になった。
- 西洋の会社制度を訳すときに「株」を使って、会社の持ち分=株式が定着した。
だから「株って名前」は、見た目は不思議だけど、意味としてはとっても納得できるんだ。

ふーん、よくわかったよ!あたしもいつか株をちょこっと持ってみたいなぁ…お兄ちゃん、一緒に勉強してね?(チラッ)
もちろんだよ、株実ちゃん。まずは基礎をゆっくり覚えて、リスクや権利の意味も理解しよう。分からないことがあればいつでも聞いてね。
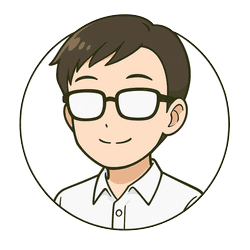
おまけ:覚えておくと便利なワード
短くチェックリスト。
- 株(かぶ):会社の持ち分のこと。
- 株式(かぶしき):株というしくみ全体の言い方。
- 株主(かぶぬし):株を持っている人。会社のオーナーの一部。
- 配当(はいとう):利益の分け前。

うん!覚えた!あたし、これでだいぶお兄ちゃんに近づけたかな?(にっこり)
十分だよ、株実ちゃん。次は実際の株の買い方やリスクの話をしようか。
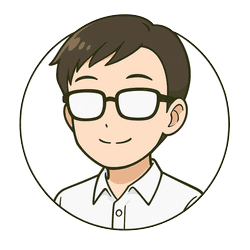
最後まで読んでくれてありがとう!語源や言葉の意味を知ると、投資もただの数字じゃなくて歴史や文化とつながって見えてくるよ。次回はもっと実践的な話をするね。